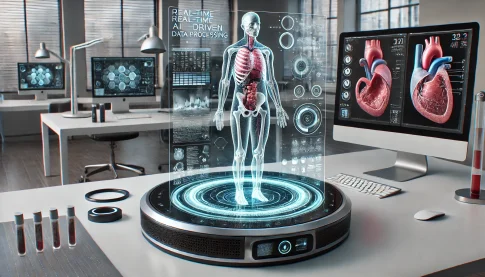朝の光が窓から差し込んでいた。真琴は目を覚まし、天井を見つめた。いつもの部屋、いつものベッド。しかし、何かが違っている気がする。
彼女は起き上がり、部屋の中を見渡した。机の上には絵の道具が並んでいる。スケッチブックを開いてみると、描きかけの風景画があった。しかし、それが何を描いたものなのか、思い出せない。
「これ、いつ描いたんだろう……」
不安が胸をよぎる。真琴は自分の記憶をたどろうとした。昨日は何をしていたのか。学校で誰と話したのか。母親の顔さえも、ぼんやりとしている。
そのとき、階下からもう一人の真琴の声が聞こえた。
「おはよう、起きた?」
真琴は階段を下り、リビングに向かった。もう一人の自分がキッチンで朝食の準備をしている。
「おはよう……」
真琴は小さな声で挨拶した。しかし、彼女の表情もどこか曇っている。
「何かあったの?」
もう一人の真琴が心配そうに尋ねる。
「実は……記憶が曖昧になっているの。昨日のことや、家族のことが思い出せなくて」
その言葉に、もう一人の真琴も驚いたように目を見開いた。
「私もなの。今朝起きたら、頭がぼんやりしていて。大切な何かを忘れている気がするの」
二人はソファに座り、互いの顔を見つめ合った。不安が募る。
「一体、何が起きているのかしら」
真琴は手元のカップを握りしめた。温かい紅茶の香りも、どこか遠くに感じる。
「何か手がかりを探そう。このままだと、自分たちが誰なのかさえわからなくなってしまう」
もう一人の真琴が提案した。
「そうね。まずは、家の中を探してみましょう」
二人は家中をくまなく探し始めた。古いアルバムや、引き出しの中の手紙。しかし、どれも見覚えがないものばかりだった。
「おかしいわ。写真に写っている人たちの顔が、全く思い出せない」
真琴はアルバムをめくりながら呟いた。
「この人は……私のお母さんのはずよね?」
もう一人の真琴も写真を指差す。しかし、その顔は霞んで見える。
「どうして……」
二人は途方に暮れた。自分たちの存在が薄れていくような感覚。
そのとき、書斎の奥にある古い本棚に目が留まった。埃をかぶった古い日記帳が一冊、ひっそりと置かれている。
「これ、見たことがある気がする」
真琴はそっと日記帳を手に取り、表紙をなぞった。革のカバーには、イニシャルが刻まれている。「M.M.」
「私たちのイニシャルだわ」
二人は顔を見合わせ、日記を開いた。中には丁寧な字で日々の出来事が綴られていた。
「これは……私たちの日記?」
読み進めるうちに、少しずつ記憶の断片が蘇ってくる。学校での出来事、好きな絵のこと、そして心の中の葛藤。
「ここに、私が美術部で絵を描いていることが書かれている」
「私も同じだわ。でも、不思議ね。全てが二人のことのように感じる」
日記の最後のページには、こう書かれていた。
「自分が誰なのか、わからなくなってきた。心の中で二つの自分が存在しているような感覚。このままでは、どちらが本当の自分なのか見失ってしまう」
真琴はページをめくる手を止めた。
「二つの自分……」
もう一人の真琴も沈黙した。
「もしかして、私たちは……」
言葉にならない思いが胸に込み上げる。
「自分たちが同一人物で、心の中で分裂しているのかもしれない」
真琴は静かに言った。
「でも、どうして?」
「きっと、自分自身と向き合うことができなかったから。孤独や苦しみから逃れるために、心が二つに分かれたのかもしれない」
二人は互いの手を握り締めた。その温もりが、確かなものであることを感じる。
「でも、これからは一緒に記憶を取り戻していこう。自分自身を受け入れるために」
もう一人の真琴が微笑んだ。
「そうね。過去と向き合って、前に進むために」
二人は再び日記を読み進めた。そこには、自分たちの本当の思いが綴られていた。絵を描くことへの情熱、誰にも言えなかった秘密、そして未来への希望。
「自分のセクシュアリティに悩んでいたことも書かれている」
真琴はそっと呟いた。
「でも、それも私たちの一部。受け入れていこう」
二人は窓の外を見た。夕日が差し込み、部屋全体が柔らかな光に包まれている。
「これからは、自分自身を大切にしていきたい」
真琴は深呼吸をした。心の中の霧が少しずつ晴れていくのを感じる。
「一緒に頑張りましょう」
もう一人の真琴が優しく言った。
「うん、ありがとう」
二人は抱き合い、静かな時間が流れた。
その夜、真琴は穏やかな気持ちで眠りについた。夢の中で、彼女は一つの道を歩いていた。遠くには光が見え、その先には新たな未来が待っているようだった。
目覚めたとき、彼女は自分が一人でベッドにいることに気づいた。もう一人の真琴の姿はなかった。
「夢だったのかな……」
しかし、手元にはあの日記があった。彼女はそれを抱きしめ、静かに微笑んだ。
「これからは、自分自身と向き合っていこう」
窓の外には、新しい朝が始まっていた。
第7話 失われた記憶の欠片